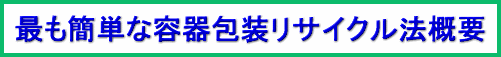
 事業者(再商品化義務の発生) 事業者(再商品化義務の発生) |
|
市町村によって分別収集され、分別基準適合物となった容器包装廃棄物を自らが製造・販売した量・金額に応じて、再商品化(リサイクル)義務が生じます。
|
| 「特定容器利用事業者」とは、事業において販売する商品にこれら「特定容器」を用いる(使用する)者を指し、中身製品の「製造・加工・販売」業が対象となる(輸入業を含む)事業者です。 クリーニング業で商品返却の際に用いるポリエチレン製袋、宅配便で用いる段ボールケースなど「サービス」業において「特定容器」を用いる場合は対象外です。
「特定容器製造等事業者」とは、これら特定容器を製造する者を指します(輸入業を含む)。
特定包装は、容器包装のうち上記の特定容器を除いたものです。これは事業者がそれを利用する段階で容器・入れ物としての形をなしていないものを指し、具体的には包装紙、ラップ、シュリンクフィルム包装の1部など商品を「包む」もののことです(商品の表面積の2分の1以下の場合は「包む」に当たらない)。
「特定包装利用事業者」とは、事業において販売する商品にこれら「特定包装」を用いる者を指します(輸入業者を含む)。
再商品化
①指定法人への委託(第3者機関にリサイクルを委託)
②独自ルートによる再商品化(再商品化の認定)
③自主回収(店頭からのリターナブルなど) |

