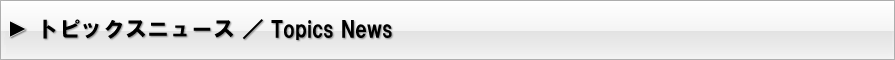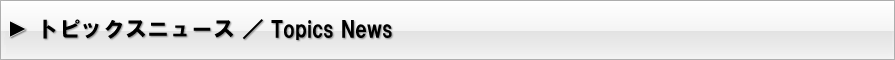【設備の構造】
熱分解設備の構造は、炭化水素油または炭化物を生成する場合については、改正施行規則第1条の7の2第1号に定められた。熱分解室内の廃棄物を燃焼させない構造や熱分解室内の温度等の保持とその測定、排出された炭化物等の冷却、処理に伴って生じたガスの適正処理について規定されている。
構造は、原則として酸素が外部から熱分解室内に供給されることなく、可燃物が燃焼を継続するために必要な酸素濃度である限界酸素濃度をおおむね上回らない程度の状態で廃棄物が加熱され、廃棄物中の有機物が熱分解される構造であることとしている。
熱分解室内を処理の対象となる廃棄物の種類等に応じ、炭化水素油や炭化物を生成するために必要な温度・圧力に設定し、それを適正に保つ構造である必要があり、熱分解室内の温度・圧力が適正に保たれていることを確認するため、これらを定期的に測定することができる構造であることとした。一定の圧力を加えない場合は、保持や測定ができる構造は必要ない。
排出された炭化物については、発火しない温度まで冷却できる構造であることとされた。なお、処理に伴って生じた不要な炭化物は、燃え殻に該当するとしている。
ところで、熱分解に係る処理基準について定めている箇所で、「熱分解し、炭化水素油または炭化物を生成する場合」と細かく言いまわしているのには理由がある。廃棄物処理法で別途に処理基準が定められている「焼却」と区分するためだ。
施行令・施行規則で新たに処理基準が定められた「熱分解」では、これを行う設備は処理に伴って生じた塩化水素、炭化水素などの不要なガスについては、薬液洗浄や活性炭吸着などによりガスを燃焼させることなく適正に処理できる構造であることとした。このガスをその設備で燃焼させる場合は「焼却」に該当し、焼却に係る諸基準が適用されることになる。
ただし、「再生利用を目的として炭化水素油を生成する場合は、生成される炭化水素油の重量が処理した廃棄物の重量の40%以上で、かつ、処理に伴って生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスの重量が、処理した廃棄物の重量の25%以下の場合」は「熱分解」の範ちゅうの「油化」とされ、この場合だけは、処理に伴って生じた不要なガスを燃焼するものは「焼却」に該当しない。
また、再生利用を目的として生成される炭化水素油は、廃プラスチック熱分解油に係る標準仕様書(TSZ0025)に適合するなど他に有償売却できる性状を有し、他の施設で燃料または原料として利用されることが可能なものであることとされている。
一方、一般的な業界用語となっている「炭化」は、この「熱分解」の処理基準について記されている箇所では使われていない。
「炭化」といっても、処理に伴って生じたガスを燃焼させることなく適正に処理できる構造をもつものは法律上は「熱分解」に該当し、燃焼するものは「焼却」に該当することになるためだ。
さらに、「熱分解」であって「炭化水素油または炭化物を生成する場合」以外のものについてもふれられている。廃棄物中の有機物を燃焼させることなく高温状態で熱分解し、酸化鉄などの金属酸化物と反応させる場合(=高炉還元材としての利用のこと)などがこれに該当するが、この場合は、熱分解に必要な高温状態に設定し、それを適正に保持できる構造であることなど生活環境保全上の支障の発生を防止する措置を講ずることが必要であるとした。
【方法】
廃棄物処理法施行令第三条第二号ロに規定する環境大臣が定める熱分解の方法は、今年1月12日に公布された環境省告示第1号に定められている。
これによると、例えば、炭化水素油または炭化物を生成する場合は、熱分解処理に伴って生じたガスの排出口以外からの漏えい防止、排出口からの残さの飛散防止と黒煙の排出防止、熱分解処理に伴って生じたガスの処理についてふれられている。
ガスの漏えい防止については、熱分解室および熱分解室からガスの排出口に至る配管などに隙間や破損部分がない設備を用いるなどの対応をとることが必要になる。
残さの飛散防止では、処理量を適正に保つとされた。また、「油化」で炭化水素油として回収されないガスを燃焼する場合は、燃焼室に十分な量の空気を供給させる他、必要に応じて集じん器を設けるなどにより熱分解を行うことが必要であるとしている。 |