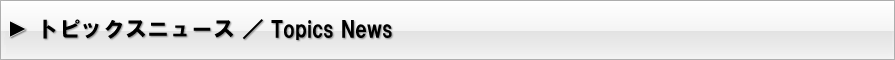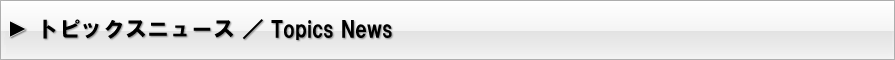2004年の廃棄物処理法改正で、廃棄物が地下にある土地で施行令で定めるものについて都道府県知事または保健所設置市の市長が「指定区域」として指定し、その指定区域における土地の形質変更に係る届出などの義務を課す仕組みが創設された。これを受け、04年12月28日、改正施行令が公布され、指定区域の範囲が定められた。
指定区域とされたのは、 廃止の確認がされた最終処分場の埋立地 廃止の確認がされた最終処分場の埋立地
 廃止の届出がされた最終処分場の埋立地 廃止の届出がされた最終処分場の埋立地
  ・ ・ 以外の埋立地(継続的にまたは反復して埋立処分が行われた埋立地であって環境省令で定めるものまたは環境省令で定める生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置が講じられたもの) 以外の埋立地(継続的にまたは反復して埋立処分が行われた埋立地であって環境省令で定めるものまたは環境省令で定める生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置が講じられたもの)
ーーとされた。ちなみに、ここでいう「埋立地」という用語は実際に埋立処分する場所(区画)のことで、「最終処分場」という用語は埋立地や擁壁、水処理設備などの総体のことになる。
まず、「 廃止の確認がされた最終処分場の埋立地」とは、98年(平成10年)に最終処分場の廃止にあたって都道府県知事が廃止基準に沿って確認するという制度が施行となった以降に、廃止となった最終処分場の埋立地をさす。また、「 廃止の確認がされた最終処分場の埋立地」とは、98年(平成10年)に最終処分場の廃止にあたって都道府県知事が廃止基準に沿って確認するという制度が施行となった以降に、廃止となった最終処分場の埋立地をさす。また、「 廃止の届出がされた最終処分場の埋立地」とは、92年(平成4年)に最終処分場の廃止の届出が義務付けられた以降に、廃止となった最終処分場の埋立地をさす。 廃止の届出がされた最終処分場の埋立地」とは、92年(平成4年)に最終処分場の廃止の届出が義務付けられた以降に、廃止となった最終処分場の埋立地をさす。
廃止の届出制度は98年に廃止の確認制度へと内容が強化された訳だが、少なくとも92年に廃止の届出制度が施行された以降に廃止されたものについては、「廃止されたことが何らかの形でわかっている」(環境省)ということになる。この2つは、改正施行令で定められた。
もうひとつの「  ・ ・ 以外の埋立地(継続的にまたは反復して埋立処分が行われた埋立地であって環境省令で定めるものまたは環境省令で定める生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置が講じられたもの)」は、3月28日に公布された改正施行規則で詳細が定められた。 以外の埋立地(継続的にまたは反復して埋立処分が行われた埋立地であって環境省令で定めるものまたは環境省令で定める生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置が講じられたもの)」は、3月28日に公布された改正施行規則で詳細が定められた。
ここでいう環境省令で定める埋立地とは、
・77年(昭和52年)に施設設置の届出制度が施行されて以降、設置の届出がなされた最終処分場であって廃止されたもの
・ミニ処分場および旧処分場(70年(昭和45年)の廃棄物処理法の施行前に埋立処分が開始されたものは、法の施行時において埋立処分の用に供されていたものに限る。)であって廃止されたもの(自社処分場を除き、市町村または最終処分業者により設置されたものに限る。)
ーーとされた。
これらはつまり、設置の届出による情報か、処理業の許可による情報かはともかくとしてその最終処分場についての何らかの情報があるものということである。逆にいえば、ミニ処分場や旧処分場であって排出事業者による自社処分場に該当するものは、それを把握するための情報を得ることが困難なため、この規制対象に入っていないということである。
一方、「環境省令で定める生活環境の保全上の支障の除去または発生の防止のために必要な措置が講じられたもの」としては、廃棄物が不法投棄された場所について遮水封じ込めや原位置覆土などがなされたものをいう。 |